借金過多の故人
17年3,000件以上で10件ほどですから決して多くはありませんが、稀に資産(預貯金・動不動産)より多い借金のある遺産を残す故人の場合、多くの家族親族は『相続放棄』を行う事になりますので過去の経験則と法律について書いてみます。
相続放棄の手続き期限
「自分が相続放棄をする必要があると分かった日(逝去した日とは限りません)」から3か月以内に手続きを開始する必要があり、負債内容の確認等で時間が必要な時は家庭裁判所に申請すれば大抵の場合3か月の期間延長が認められます。
相続放棄の可能性があったらしてはいけない事
- 被相続人の預貯金を引き出す事・通帳解約
- 賃貸アパートの解約
- 家具や家電などの遺品整理や販売
- 車、スマホなどの処分
- 被相続人の資産(お金)で故人の借金や税金を支払う
- 被相続人の資産(お金)で入院費を支払う
上記のような行動は『故人の財産に関与した』事になり、相続放棄が出来なくなる可能性があるので要注意(家庭裁判所で確認しましょう)しかし家族等の所持金で入院費を支払う分のは問題ありませんので、道徳・倫理観からしても家族親族で支払うべきと思えます。
相続放棄の手続きをする「家庭裁判所」
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所ですが、まずは最寄りの家庭裁判所で「相続放棄の仕方」と上記の「してはいけない事」「相続放棄が必要な人」など聞き、その後の流れを聞けば裁判所で教えて貰えるでしょう。
相続放棄は第3順位まで
① 配偶者はいかなる場合も法定相続人(相続放棄必須)
② 子供・孫(相続する親が逝去してる場合)は第1順位(相続放棄必須)
①②の親族は相続放棄の手続き必須です
②の子供(孫)が相続放棄すると、第2順位の ③ 親(逝去してる場合は祖父母)の相続放棄が必要となり、①②③が相続放棄すると、第3順位の ④兄弟姉妹の相続放棄が必要となります。通常のケースでは第4順位の甥姪は放棄する必要はありません。
また連帯保証人も相続放棄はできますが、連帯保証債務を免れることはできませんので、債権者から返済を求められたら応じるしかありません。
手続き・費用
自分で相続放棄すれば¥3,000~¥5,000ほどですが、司法書士・弁護士に依頼すると3万円~10万円ほど掛かると言われますので頑張って自分でしましょう。
配偶者・子供達が相続放棄した後、第2順位の人達が相続放棄、続いて第3順位の兄弟姉妹という順で手続きすることになります(通常3週間~1か月程度)
相続放棄しても受け取れるお金
「葬祭費・埋葬料」
国保から支給される葬祭費(健康保険は埋葬料)は、故人に支給されるものでなく葬祭を行った人に支給されるものですから、相続放棄とは関係の無い支給となるはずです。
「未支給年金」
また被相続人が存命中に支給されて年金は故人遺産ですが、逝去日以降に支給される未支給分は同居(財布を同じくる者)者に支給されるものなので、未支給年金も同様と思われる。
「常識範囲の葬式代」
常識の範囲内で行われた葬式代ついては、死体を放っておけば死体遺棄の罪もあり、死体火葬は当然の常識と思われる事から、一定額の葬式代も認められるのでは? と思われるので、家庭裁判所で確認されると良いでしょう。
自分で行うからスキルがアップする
死後手続きは家族がいる限り必ず発生するものですから、安直に税理士・司法書士・行政書士に依頼するのではなく、初めての時は大変に思えても自分で行う事を強く勧めます。2回目は家族に教えながら進めれば自分だけでなく子供達もスキルが得られ費用も抑えられます。
あんしんサポートも最初はチンプンカンプンでしたが『残る家族の生活を守る』には葬式代だけでなく、様々な費用を抑える必要から学び実践して今があります。
どんな博学な人でも初めてや、無知の時はあったのですから、知らない事は調べたり、教えて貰えば良いだけのこと10年後は貴方も博学になってるはずです。
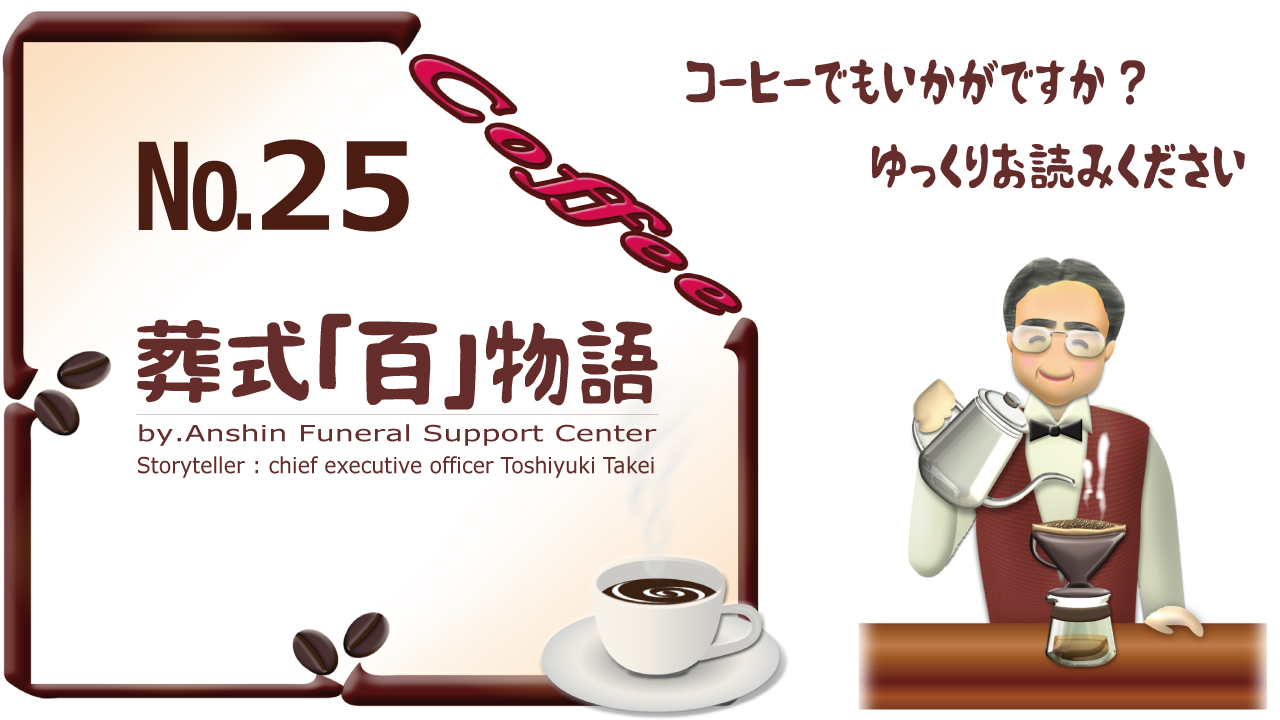


コメント